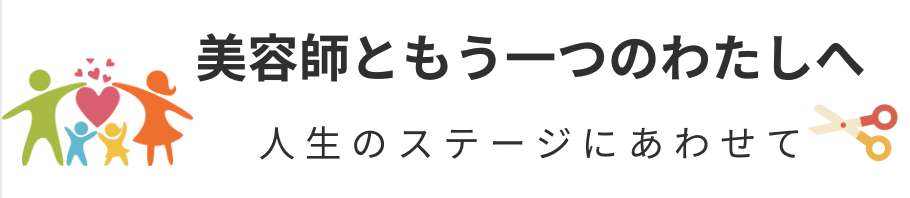ヨガに興味を持ってくださり本当にありがとうございます。新米学び中のchiharuです。私自身、40代になってから経験した自律神経の大きな乱れをきっかけに、ヨガの道へと導かれました。以前の私は、毎日を急いで生き、自分の心の声を聞く余裕もなく、ある日突然、強烈なパニック発作や、血の気が引いて頭が真っ白になるような恐怖に襲われるようになりました。それは体が恐怖を記憶し、「また同じことが起きるのではないか」と脳がすぐに警報を鳴らしてくるような、些細な身体の変化にも敏感で辛い日々でした。そんな私が救いを求めて辿り着いたのが奥深いヨガの世界です。

多くの人がヨガと聞くと、身体が柔らかい人がするものと思うかもしれませんが、お伝えしたいのは、身体を整えるのはもちろんですが、そのマットを降りた後も、一瞬一瞬の選択を支えてくれるのがヨガの力です。特に私のように自律神経の不調に悩む方にとって、ヨガはただの運動ではなく、穏やかで安全に過ごすための実践的な知恵となります。
自律神経の乱れから始まった私のヨガとの日々
私のヨガとの出会いは、耳鳴りや激しい動悸、不安感といった自律神経の不調からでした。最初は「深呼吸が大切」と本を読みましたが、継続的な効果は得られず、もっと身体を動かすことをしないといけない。と漠然と思い、そんな時目にしたのが「ヨガで自律神経を整える」という記事です。藁にもすがる思いで始めた毎日の太陽礼拝。最初の練習直後、心がスーッと晴れて前向きになった感覚は、今でも鮮明に覚えています。必死に続けた2ヶ月間が、元気な自分に戻る大きな一歩となりました。
ヨガはポーズだけじゃない。「くびき」の意味を知る
ヨガスクールで確か一番最初の講義で「ヨガとは何だと思いますか?」と先生に問われた時、私はマットの上でポーズを取って体と心を健康に。みたいなことだと思っていました。しかし先生からのお話は「繋がり」や「結合」を意味するもので、語源は牛と荷台をつなぐくびき(ユジュ)からきていると知りました。ポーズ(アーサナ)はヨガの一部に過ぎないということ。その歴史の長さが物語るように、ヨガは心、体、そして真実の自己を探す、とても奥深いものでした。
身体を柔らかくする単なるエクササイズではありませんでした。
幻の世界を生きる私たち
ヨガの哲学では、私たちが生きるこの物質世界は、苦しみや自我(エゴ)を生み出す幻の世界(マーヤ)だと説かれます。そして、その苦しみに巻き込まれてしまうのは、一瞬一瞬の自分の判断だと考えられています。私が講義で感銘を受けた聖典『バガヴァッド・ギーター』(神の歌)に描かれるものはまさに私たちが日々直面する自分の心の中のことだと解釈できました。そこには、強く立ち上がれる自分もいれば、エゴや執着に負けて逃げ出したくなる自分もいる。わたしたちの心の中身そのものでした。
敵はネガティブな「思考」立ち上がる勇気
自律神経の乱れからくる恐怖は、ネガティブな思考は敵として、いつも瞬時に襲ってきます。血の気が引く感覚と共に「また発作が起こる」と体が反応してしまうのです。そんな時、ギーターの教えにある「私に心を向け私を信愛せよ。アルジュナ立ち上がれ、決意をして」という一節が、私にとっての強力なメッセージとなりました。その思考は本当の私ではない。ただの思考の一つだと受け流す勇気を与えてくれます。恐怖に飲まれるのではなく、立ち上がって、前を見る決意をすること。これは私にとって大きな心の安定につながりました。
「タパス」とは継続の実践、その先にあるもの
歯磨きのような習慣へ
私がブログのタイトルにしたタパスとは、サンスクリット語で「苦行」「燃やす」という意味です。熱意をもって継続する努力を指します。苦行と感じるということは自分自身の許容範囲の外にあるから辛い。辛くても何度も何度も繰り返し行うことで自分の許容範囲の中に入ります。その時その対象に対しての執着がなくなる。それこそが苦行の先にあるものです。すぐに結果が出にくい心の制御や習慣化には、このタパスが不可欠です。『ヨーガ・スートラ』にも、「長い間 休みなく 大いなる真剣さをもって励まれるならば、堅固な基礎を持つものとなる」という教えがあります。毎日、同じ場所で座り整える規律を持つこと。これは決して簡単ではありませんが、歯磨きをするように、当たり前の日常の習慣としてヨガに向き合うことが、心の土台を固めることにつながります。それが少しのことではくじけないという土台になる。特に感覚器官は強烈だという教えも記されていました。物質世界と私達の感覚器官はつながってしまいます。「目で見ているこの場所は前にパニック発作が起きた場所だ。」「この頭がぼーっとする感覚なんか恐れに襲われる予感がするな」そんな時その思考に支配されるのか、それともこちらが支配するのかは日頃のタパスに真剣に取り組んでいるのか、気が向いた時だけやっているのかでは大きなちがいが生まれます。ヨガを実践していくことで自分のマインドに振り回されない土台が身につくという感覚があります。
迷ったら「ダルマ」に立ち戻る。周りの笑顔が道しるべ
ヨガ哲学には、ダルマ(義務)という教えを大切にしています。私たちには、母として、妻としてや職場での役割があり、その都度、何を行うべきかを見極める必要があります。損得勘定や、やりたいかやりたくないかで判断してしまいがちな私たちに、先生からいただいたヒントは「調和を感じられているかどうか」を意識すること。ヒントは「周りが笑顔になっているかどうか」というとても分かりやすいものでした。迷った時、このシンプルで実践的な教えに立ち戻ることで、自分の行動を正すことができます。
自律神経の不調とともにヨガを学び、今も学びを続ける新米だからこそ、私はヨガの実用性を実感しています。私と同じように自律神経の悩みに向き合っておられる方に前を向いて歩んでいけることを心から願っています。